北杜市須玉町にある、「須玉歴史資料館」に行ったり、地域の歴史にくわしい小沢和男さんを先生として招いたり、身延町の「湯之奥金山博物館」の、学芸員の小松美鈴さんに「出張博物館」を開いてもらったり、地域の「のろし研究会」の人たちを招いて、のろしを実際に上げてみるなどの、体験活動もしてきました。
いろいろな活動を進めながら、私たちの住んでいる増富について、調べたことをここにホームページとして発表することができました。皆さん、私たちの調べた結果をじっくり見て、私たちの住む増富を知るとともに、ぜひ感想を送ってください。(平成17年10月14日公開)
| (授業の様子) | |
| (児童が作成したページ) | |
| (児童が作成したページ) | |
| (担任が作成したページ) | |
| (児童が作成したページ) | |
| (児童が作成したページ) | |
| (担任が作成したページ) |
 |
 |
| ▲金山 | ▲金山坑道近くのザレ場(廃石捨て場) |
 |
本谷川上流の金山沢右岸の金山平には、金山の伝承が伝えられています。「往古金鉱があり、武田氏の時代には400戸の人家があり、金山千軒といわれた。」(北巨摩郡史)といいます。金山平の有井館には、水場から明治20年代に発見された鉱山臼があり、金山には、御岳型黒雲母花崗岩の地層のペグマタイトに掘り込まれた坑道3カ所が知られていました。須玉町史編纂のための調査として、金山金山遺跡の調査が1995年に、塩山市黒川金山・身延町湯之奥金山に次ぐ、甲斐金山として3番目の総合調査が行われています。 金山山腹の標高1610m〜1530mにかけて11カ所の坑道、試掘抗(狸堀)数カ所を確認することができました。坑道は縦長の金桶押法の坑道で、1〜20mの長さで鉱脈を追って険しい山腹に掘り込んでいます。採掘された時期は、武田信玄の活動していた戦国時代から江戸時代までだといわれています。 また、金山の北側にある「魔子の人穴」も金を採掘した鉱山の跡だといわれています。 |
| ▲金山坑道入り口 |
 |
 |
| ▲金山平にある金山節の石碑 | ▲金山平で見つかった金鉱を砕くための石臼 |
ハアー 雁が来るのに 主は金山へ ハアー 軒のつばくろ 金山ゆかば
かせぎよいゆうて おでなされた この子無事だと いうとくれ
ハアー ひるはひぐらし 夜は夜鳴きどり ハアー 愛しい心と 金山水車
星の数ほど 主を思う 雪の中でも 止まりゃせぬ
ハアー 祭り太鼓が 雷さまか ハアー 御岳の裏道 よく来てくれた
耳をすませば 胸がなる さどやぬれつや 滝しぶき
ハアー 里を離れて 金山ぐらし ハアー 吹くな木枯らし ゆするな裏戸
月が鏡で あればよい 火の黄金の 粉がとぶ
ハアー 小ぶち沢から 金山三里
持たせてやりたや 凍豆腐
 |
| ▲サイクガエリ地区 |
武田信玄公の頃、金山で金鉱の採掘をしていた人々が、金山が廃坑になったので、それぞれ四散しました。しかし、大部分の人は、今の和田集落に永住するようになったといわれていて、この地を「採鉱帰り」といいました。それが後になって「サイクガエリ」になったといわれています。
 |
 |
| ▲金峰山 | ▲五丈岩と金峰山頂 |
 |
| ▲金山平北にある木暮理太郎のレリーフ |
深田久弥さんは「日本百名山」の中で、『われわれ山岳党の大先輩木暮理太郎氏に次のような言葉がある。
金峰山は実に立派な山だ。独り秩父山脈の中に斬然 頭角を抜いているばかりでなく、日本の山の中でも第 二流を下る山ではない。世に男の中の男を称えて裸 百貫という諺があるが、金峰山も何処へ放り出しても 百貫の貫禄を具えた山の中の山である。
金峰山に対してこれ以上の讃辞はあるまい。
私もそれに賛同する。秩父の最高点はこれより僅か数米高い奥千丈岳に譲るにしても、その山容の秀麗高雅な点では、やはり秩父山群の王者である。』と記しています。
 |
| ▲千代の吹き上げ |
神のたたりと恐れた夫は、七日間断食してお千代の罪を許してもらおうと祈り続けると七日目に突然、ヒューという音とともに谷底から吹き上げた風にのって、死んだはずのお千代が、元気な姿で夫のもとに帰ってきました。それからこの谷を「千代の吹き上げ」というようになったそうです。
 |
| ▲金峰山・瑞牆山の登山道途中にある里宮 |
ところが幾百年の霜星の中に、社屋の腐朽や神霊の破損を見るに至ったため、昭和45年10月、黒森地区民こぞってその再建を図り、里宮ゆかりの大峰金峰山より修験道の行者を招き、本宮の再建と神霊の御遷宮をし、現在に至っています。
 |
| ▲黒森地区から見た万燈火山 |
黒森の集落を見下ろすところに位置し、昔はノロシ台があったともいわれています。
 |
| ▲和田地区 |
これを知った村人たちは、たいそう悲しんで、かわいそうな尼さんのために、京の空が見える山の山頂に塚を築いて手厚く葬ってあげました。
その後、この場所を「比丘尼塚」と呼ぶようになり、峠の坂道を「京のぼり」というようになったそうです。
 |
 |
| ▲白竜山徳泉寺 | ▲徳泉寺の宝筐印塔 |
宝筐印塔は、郷土の安全と繁栄を祈念して安政6年(1859年)に建てられました。小森川の巨石を切り出し、宝筐印陀羅尼経を一字一石に祈願し浄写して礎石に埋蔵した、地域の誇りともいえる石塔です。
 |
 |
| ▲正覚寺 | ▲正覚寺のお石塔 |
昔は真言宗でしたが、山梨郡和田村法泉寺末となるに及び、山号を和田山とし、臨済宗となりました。和田の西光寺・大柴の常福寺が相次いで廃寺になるや、檀徒は正覚寺檀家となったそうです。四奉行御黒印三百六坪であるそうです。
 |
| ▲浜井場の東屋神社 |
尊は、この地の猛獣・毒蛇を調伏するために破魔弓を使い、弓を立て「破魔弓場」と呼ばれたのが、後の文字の転用により今は「浜井場」と呼ばれています。
さらに尊は里人に農耕のやり方を教え、なお神戸・御門および北西方面に進み、碓氷峠を経て信濃の国に入ったと伝えられています。
 |
|
| ▲東小尾の大柴地区 |
大柴遺跡の地形を見ると、北側には山がそびえ、南側には本谷川があり、サルト沢とサカ沢に挟まれた丘陵南斜面に位置しています。また、東側には金峰山を望むことができます。このような地形から推測すると、なぜ遺跡が存在するかわかります。まず、人間が生活するに当たっては水は欠かせないものであり、縄文人の生活にとって川は重要なものでした。そして、南斜面の山間の丘は日当たりもよく、周囲の森林には木の実や獣も多く、東に神々しくそびえる金峰山や瑞牆山は、縄文人の自然物崇拝の対象として重要な役割を果たしていたと思われます。
 |
| ▲みずがき湖畔のヨシャーの温泉 |
当時の文献には、「塩川、昔山塩ヲ産シ、水一升ニテ三勺余有ト伝フ。永禄年中、今川・北条塩止ノ際、土人塩川源地塩水ヲ送リタリ韮崎下、塩前ト云ヒ、韮崎迄ハ塩前ト云フ」と書き留められています。
この文献から当時のように熊笹に水をかけて天日乾燥すると、葉に塩の結晶がかすかであるが作られました。一升の水を鍋に入れて沸騰蒸発を試みました。火にかけてから15分頃から鍋の中で透明だった水は白濁色になりました。また、お湯が完全に蒸発したと同時に、鍋の底に白い塩の結晶があらわれました。
戦時中、この地では、この水で小麦粉を練り、パンを作ったそうです。炭酸ナトリウムが強いため、「ふくらし粉」のかわりになったといわれています。また、皮膚病に効くともいわれています。
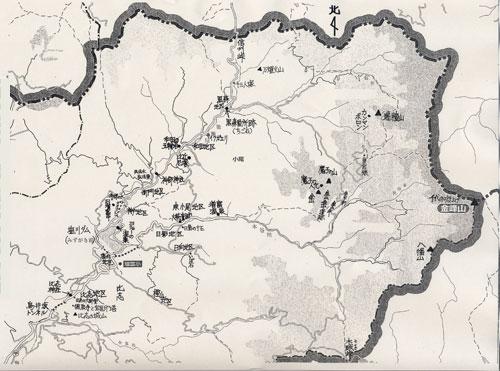
『須玉町史』通史編第1巻、資料編第1巻・須玉町史編纂委員会
『増富のむかしばなし』増富地区公民館
『増富遺跡群調査現地説明会資料』須玉町史編纂委員会
『日本百名山』深田久弥
藤原松子さん(北杜市須玉町黒森在住)