 |
 |
 |
| ▲6月22日 理科の時間を使って、まずは土の研究。 |
▲煎って水分を飛ばし、粘土について勉強しました。 |
▲8月26日 児童の祖父が採ってきた「増富の土」を使って取り組み開始です。 |
 |
 |
 |
| ▲徐々に水を入れて粘土状にしていきます。 |
▲粒の大きい礫(れき)を取り除き、上質の粘土を取り出すために、こうやって漉します。 |
▲漉(こ)した物を、数日間放置し、水分を飛ばします。 |
 |
 |
 |
| ▲9月3日 耳たぶくらいの硬さの粘土が陶芸には最適。でも、少し柔らかすぎました。 |
▲9月9日 一週間後、増富の土に陶芸用の粘土を少し混ぜてみました。 |
▲いよいよ、形にしていきます。 |
 |
 |
 |
| ▲9月30日 今日は焼き物用の窯(かま)作りに挑戦。 |
▲野焼きをするための窯を自分たちの手で作ります。 |
▲レンガを積んでいきます。 |
 |
 |
 |
| ▲“校庭の中心で窯を作る・・” |
▲これくらい積めばいいかな? |
▲手作りの窯が完成しました。 |
 |
 |
 |
▲10月1日 午前8時
七輪に火をおこし、「おき」を作ります。 |
▲その上に「もみがら」を入れていきます。 |
▲火の加減が難しいです。 |
 |
 |
 |
| ▲そして、乾燥させた小さな「箸おき」を入れます。 |
▲これで待つこと、半日。校庭の中心で窯が燃える。 |
▲これが「増富焼き第1号」。左が増富産100%の粘土で作った箸置き。窯の温度不足で黒くなってしまったようです。 |
 |
 |
 |
| ▲10月4日チャレンジ再開! |
▲粘土の扱いは慣れたもの。 |
▲この日は小皿を作りました。
このまましばらく乾燥させます。 |
 |
 |
 |
| ▲10月7日 塩川ダム近くに粘土質の土があると聞き、採掘に行きました。 |
▲見つかりました。灰色の部分が粘土質の土です。 |
▲その土を持ち帰り、くだきます。 |
 |
 |
 |
| ▲それをこして、くだききれない大きな固まりを除きます。 |
▲10月8日 昨日、細かくした土に水をいれ、さらに溶かしてつぶします。 |
▲何日間も外気にさらし、徐々に水分を飛ばしていきます。 |
 |
 |
 |
| ▲10月28日 耳たぶ状の硬さになったので、いよいよ形づくり。 |
▲先生に相談しながら、作業を進めます。 |
▲花瓶に模様を付けていきます。 |
 |
 |
 |
| ▲11月15日 自分たちで採集してきた土と焼きもの用の土を半々にしたのがこの粘土。 |
▲それをよく練っていきます |
▲その後も続々と作品を作り上げていった6年生。 |
 |
 |
 |
▲何年も眠り続けていた窯を
6年担任が復活させました。 |
▲12月9日 この窯を使って作品の素焼きを行います。 |
▲「焼けるのかなあ?」とのぞきこむ6年生。 |
 |
 |
 |
| ▲眠りから目を覚ました窯は順調に温度を上げていきます。 |
▲12月10日 「よし開けるぞ。」果たして焼けているのか?割れてはいないか? |
▲陶芸窯、復活第1弾の作品は大成功。 |
 |
 |
 |
| ▲12月13日 今日も作品作りに励む6年生。 |
▲今日はろくろに挑戦。 |
▲「ほししいたけみたい〜。」と
なかなか的を射た表現です。 |
 |
 |
 |
▲12月17日 窯は快調。
今日も新たな作品を焼いてみました。 |
▲軽くたたいてみたら、キンキンという高い音が響きました。 |
▲今回も大成功でした。 |
 |
 |
 |
| ▲1月19日 雪に埋もれそうな陶芸窯の前には今日も6年生の姿が。 |
▲ヤッター!今回も割れずに焼けました。 |
▲キャンドルライトカバーとコップが焼けました。 |
 |
 |
 |
| ▲1月21日 教室をのぞいてみると何やら作業中。 |
▲見覚えのある形・・・ |
▲あっ!校章と同じだ。 |
 |
 |
 |
| ▲自分たちで焼いた校章のプレートを卒業記念品として学校に贈る予定です。 |
▲細かい作業は担任が行います。 |
▲3人の3本の手で一つの作品を作ります。これはしばらく乾燥させます。 |
 |
 |
 |
| ▲2月8日 窯を開ける瞬間はいつもドキドキ。 |
▲担任も一緒に作った小鉢を持ってニコッ。 |
▲出番を待つ増富焼き予備軍たち。 |
 |
 |
 |
| 2月25日 今日は「釉薬(ゆうやく)」を付けます。 |
▲素焼きをした作品に、まずは撥水剤を塗ります。 |
▲そして、いよいよ作品に釉薬を付けます。 |
 |
 |
 |
| ▲ぬるっとした感触です。 |
▲この日は5年生も一緒に行いました。 |
▲釉薬をつけた作品。青銅、うずら、ソバ色に焼き上がるそうです。 |
 |
 |
 |
| ▲3月1日 作品を窯から出します。みんなドキドキ。 |
▲「わぁ〜すごい〜!!」と歓声があがりました。 |
▲どれも割れることなく、きれいに焼けました。 |
 |
 |
 |
| ▲5年生も一緒にニッコリ。 |
▲小鉢に、箸置き。落ち着いた色に仕上がりました。 |
▲まるで売り物のような光沢ですね。 |
 |
 |
 |
| ▲3月3日 今日は卒業記念品「校章プレート」を焼く日です。 |
▲いつにも増して慎重に窯の準備をします。 |
▲いよいよ窯の中に入れます。 |
 |
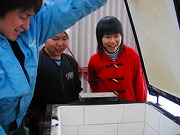 |
 |
| ▲3月4日 校章プレートは割れずに焼けたでしょうか? |
▲3人から笑みがこぼれます。 |
▲割れることなく焼けました。 |
 |
 |
 |
| ▲やったね。大成功です。 |
▲「先生、ここで落とさないでね。」 |
▲雪が激しく降る中、自分より作品を傘で守ります。 |
 |
 |
 |
| ▲3月7日 今日は花びんに釉薬をつけます |
▲今回は2色の釉薬をつけました。 |
▲焼き上がりはどうなるのでしょう? |
 |
 |
 |
| ▲3月9日 窯をぼう然と見つめる6年生の姿が・・・。 |
▲なんとマグカップが変形してしまったのです。 |
▲「何が原因だろう?」とみんなで苦笑い。 |
 |
 |
 |
| ▲これもいい思い出になりますね。 |
▲釉薬の付けた方を工夫したことで、こんなにステキな花びんが焼き上がりました。 |
▲その横にひっそり並ぶマグカップ。 |
 |
 |
 |
| ▲3月16日 今日で「増富焼き」も最終。5年生も一緒です。 |
▲さて、大皿は焼けたかな? |
▲あらら?そこにあるのは、真っ平らの物体です。 |
 |
 |
 |
| ▲窯の台にはり付いてしまいました。どうやら失敗です。 |
▲「何?何?どうなっちゃったの?」と不思議顔。 |
▲気を取り直して最後の記念写真を。 |
 |
 |
 |
| ▲3月23日 卒業式。いよいよ校章プレートの贈呈です。 |
▲式台に掲げられた校章プレート。 |
▲一年間の集大成が今ここに。完成おめでとう。 |



